BEMとは何か? ─ CSS設計が必要とされた背景
CSSWebサイト制作の現場では、CSSはしばしば「膨らみすぎて制御不能になる」問題に直面します。
例えば、あるページにボタンのスタイルを追加したら、別のページのボタンまで崩れてしまう──そんな経験はないでしょうか。
これはCSSの特性であるカスケード(継承と上書き)に起因します。便利な仕組みである一方で、規模が大きくなるほど「どのルールがどこに効いているのか」が不透明になり、修正が修正を呼ぶスパゲッティ化が起こりやすいのです。
こうした背景から、「CSSを設計する」という考え方が必要になりました。
BEMの登場と基本ルール
BEM(Block, Element, Modifier)は、2010年代にロシアの検索サービスYandexが大規模開発の中で生み出した命名規則です。
ポイントは 「役割を名前で明示する」 こと。
- Block:独立したコンポーネント(例:card)
- Element:Blockの一部として存在する要素(例:card__title)
- Modifier:見た目や状態のバリエーション(例:card–featured)
<article class="card card--featured">
<h2 class="card__title">おすすめ商品</h2>
<p class="card__desc">期間限定セール中</p>
</article>
このようにクラス名をつけると、構造と役割が明確になり、誰が見ても「どのCSSがどこに効いているのか」が分かりやすくなります。
一般的なBEMのイメージと受け止められ方
BEMは特別なツールを導入しなくても、「命名ルールを守るだけ」で始められるのが特徴です。
そのため大規模サイトやチーム開発では「保守性が上がる」「クラスの衝突が減る」と評価され、現在でも一つのスタンダードとして紹介されることが多い手法です。
一方で「クラス名が長くなる」「小規模サイトでは大げさ」という声もあり、現場の評価は分かれています。
まずはBEMを知っておく価値
BEMはCSS設計の数ある手法のひとつであり、万能の正解ではありません。
しかし「なぜ命名規則が必要なのか」を理解する入口として、非常に学びやすいアプローチです。
次回は、BEMが実際にどんな業務や業界で役立つのかを掘り下げていきます。
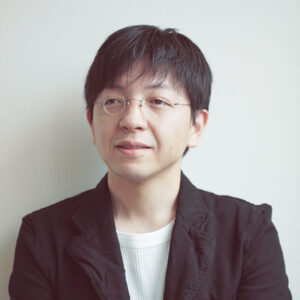
- 執筆者:西部俊宏
- 株式会社Webの間代表取締役。上場企業でのSEOやWebサイト構築実績多数。ECサイトのカスタマイズ経験も多数あり。
- 会社概要はこちら
「ECサイトをより便利にしたい」「もっと集客したい」ECカスタマイズはお任せください