プラグインが“速度の敵”になるとき|EC-CUBEが抱える構造的ボトルネック
EC前回は、EC-CUBEプラグインがEC運営における“拡張の自由”を支える仕組みであることを紹介しました。
しかしその利便性の裏には、PageSpeed Insights(PSI)での評価に影響する構造的な課題が潜んでいます。
今回は、なぜプラグイン導入がサイトを重く見せてしまうのか、その仕組みを掘り下げます。
便利さの裏にある「クライアント処理構造」
EC-CUBEのプラグインは、できるだけ多くの環境で動作するよう設計されています。
そのため、サーバー設定(cron や CLI コマンド)を前提としない クライアント側での処理 が採用されるケースが多くあります。
たとえば、以下のような機能が典型的です。
- バナークリックの計測や表示切り替え
- おすすめ商品・ランキング商品の動的読み込み
- 閲覧履歴に応じたレコメンド表示
- ポップアップやスライダーのアニメーション処理
これらはページの読み込み後に JavaScript や Ajax を使って実行される構造になっており、HTML の初期描画とは独立して動作します。
クライアント処理で発生する「見えない遅延」
こうした構造はユーザーにとって一見スムーズに見えるものの、PageSpeed Insights の測定上では「LCP(最大コンテンツの描画)」や「INP(操作応答)」などに影響します。
ブラウザ側での処理は以下のような流れをたどります。
ユーザーがページを開く
↓
HTMLが読み込まれる
↓
JavaScriptが解析・実行される(ここで一時的に停止)
↓
Ajaxなどで追加データを取得
↓
DOM更新 → 画面に反映
この「JavaScript解析・実行 → DOM更新」の間は、ブラウザが再描画を保留するため、画像やテキストの最終的な配置が確定せず、LCP の測定が完了しません。つまり、「見えているけれどまだ安定していない」という状態が続くのです。
PageSpeed Insights における影響の出方
PageSpeed Insights の指標では、こうしたクライアント側処理が以下のように分類されます。
| 指標 | 発生しやすい影響 | 原因の例 |
|---|---|---|
| LCP(最大コンテンツの描画) | 遅延 | 画像やテキストの描画がJavaScript実行後に確定 |
| INP(操作応答性) | 遅延・一時フリーズ | JavaScriptイベントの解析・処理待ち |
| TBT(メインスレッドのブロッキング) | 上昇 | 重いライブラリや同期通信処理 |
| CLS(レイアウトシフト) | 増加 | 後からDOM要素が追加・再配置 |
数値そのものがすべて悪化するわけではありませんが、JavaScriptの動作タイミングによって計測の基準が後ろにずれるため、「スコアが伸びにくい」状態が起こります。
サーバー側処理との違い
本来、こうした更新・集計・レコメンド処理はサーバーサイドで定期的に行うことが可能です。
しかし、プラグイン形式では以下のような制約が存在します。
| 処理方式 | 特徴 | 実装上の課題 |
|---|---|---|
| サーバー処理 | cron や CLI により定期実行できる | サーバー権限が必要、環境依存が強い |
| クライアント処理 | すべての環境で動作しやすい | JavaScript実行・描画待ちが発生しやすい |
つまり、配布型プラグインは「誰でも導入できる」ことを優先するため、ブラウザ側の負荷を前提にした設計になりやすいのです。
なぜ「非同期設計でも遅く見える」のか
中には非同期通信(async / defer)を導入しているプラグインもあります。
それでも速度評価に影響が出るのは、「LCPの要素が確定する前にJavaScriptが描画を制御している」 ためです。
- メインビジュアルの切り替え制御をJavaScriptで行っている
- Ajaxで商品情報を後から挿入している
- jQueryライブラリが複数ロードされている
例えば上記のような構成では、ブラウザが再描画を繰り返すため、体感よりも評価指標が低く出ます。
どのように付き合うべきか
プラグインは導入のしやすさが最大の利点です。しかし、PageSpeed Insights のスコア改善を目的とするなら、以下の観点で“影響の少ない構成”を意識することが重要です。
- LCP要素(メイン画像・テキスト)をJavaScript制御の外に置く
- Ajax処理は非同期化し、描画をブロックしない構造にする
- 不要なライブラリを削除・統合する
- ユーザーアクセスで発火する処理をサーバー側に移せないか検討する
次回は、同じ「おすすめ商品」「ランキング表示」といった機能を、独自開発(サーバー側処理)で軽量に実装する方法を解説します。PageSpeed Insights のスコアを落とさずに動的コンテンツを扱う実践的アプローチをご紹介します。
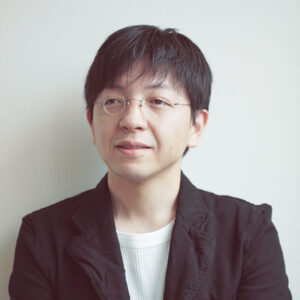
- 執筆者:西部俊宏
- 株式会社Webの間代表取締役。上場企業でのSEOやWebサイト構築実績多数。ECサイトのカスタマイズ経験も多数あり。
- 会社概要はこちら
「ECサイトをより便利にしたい」「もっと集客したい」ECカスタマイズはお任せください