Core Web Vitalsの“INP偏重”の評価にどう向き合うべきか
SEO2024年のアップデートでINP(Interaction to Next Paint)が正式にCore Web Vitalsの指標となって以降、現場では「INPをどう改善するか」が主要な議題に上がるようになりました。
一方で、INP偏重による過度な反応や誤解も目立ち始めています。本記事では、INPという指標とどう向き合い、どう扱うべきかについて整理します。
INPは万能ではない:誤った“全体最適”に注意
最近のWeb制作やSEO現場で見られる動きとして、INPスコアが悪い=サイト全体が重い/JavaScriptが悪いという短絡的な解釈が広がりつつあります。
たとえば、Search ConsoleでINPが「不良」と表示されたことをきっかけに、すべてのページの構成やスクリプトを大幅に見直そうとするケースがあります。しかし、実際にツールで計測してみると、特定ページの一部UIやフォーム処理のみが原因だったということが少なくありません。
こうした事例は実際の開発・改善相談の中でも頻繁に見られており、部分的なボトルネックを、全体的な問題と誤解してしまうことが混乱を招いているといえます。
フロント実装だけではINPは改善できない
INPが悪化しているからといって、アニメーションを削除したりDOM構造を見直したりしても効果が薄い場合があります。
なぜならINPは、ユーザー操作に対して“次のペイント”が発生するまでの遅延時間を測る指標であり、根本原因がバックエンドの処理や、非同期通信のタイミングにあることも多いからです。
- よくあるボトルネックの例
- 「送信」ボタン押下後、外部APIからのレスポンス待ち
- 非同期バリデーション処理がメインスレッドをブロックしている
- イベントリスナ内で大量のDOM操作や同期処理が走っている
このように、フロントの軽量化だけでは対応しきれないのがINPの難しさです。
スコアの“良し悪し”でなく、変化の“傾向”を追う
Search ConsoleやPageSpeed Insightsが示すINPスコアは、ユーザー環境に依存した実測データ(Field Data)に基づいています。
- 回線速度が遅い
- 古いスマートフォンを使っている
- 高トラフィックの時間帯でアクセスしている
例えば、上記のような外部要因で、スコアが一時的に悪化することもあります。
重要なのは「ある特定の数値が悪いこと」ではなく、全体として悪化傾向にあるか?改善の兆しが見られているか?という“変化の流れ”です。
スコアを「絶対的な評価」ではなく、「改善努力を可視化する相対指標」として活用することが、健全な運用につながります。
今、INPに取り組む価値とは?
INPが正式指標に採用されたことで、今後の検索評価に影響を与えることは間違いありません。しかし、LCPやCLSのように「改善しやすい要素」ではないことから、以下のような姿勢が求められます:
- 短期でのスコア改善を狙うのではなく、改善点を丁寧に絞る
- 他指標(LCP・CLS)と合わせて“体験の総合値”として捉える
- ツールやフィールドデータの読み解き方を社内で共有し、判断軸を一本化する
INPの波に、翻弄されずに乗るために
INPは、ユーザーの「操作感」に最も近い指標です。しかし、計測方法が複雑で、原因も分散しているため、安易にスコアだけを見て“全否定”したり“全修正”に走るのは逆効果です。
「このサイトのINPは悪い。でもどこがボトルネックなのか?」という問いからスタートし、着実に原因を特定していく。
この姿勢こそが、INP時代のUX改善に必要な「静かな処方箋」だと言えるでしょう。
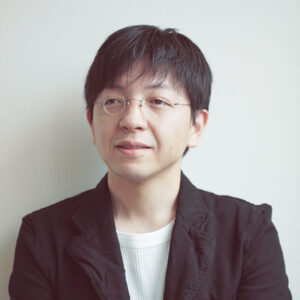
- 執筆者:西部俊宏
- 株式会社Webの間代表取締役。上場企業でのSEOやWebサイト構築実績多数。ECサイトのカスタマイズ経験も多数あり。
- 会社概要はこちら
「ECサイトをより便利にしたい」「もっと集客したい」ECカスタマイズはお任せください