BEMが業務で役立つ場面 ─ 大規模サイトとチーム開発
CSS数ページ規模のサイトであれば、CSSの管理はそこまで大変ではありません。
スタイルを追加しても影響範囲は限られ、チームメンバーも数人程度。
「とりあえずのクラス名」でも意外と回ってしまいます。
しかし、これが数百〜数千ページ規模のECサイトやメディアサイトとなると話は別です。
複数人が同時にCSSを書き、コンポーネントを使い回すなかで、クラスの衝突や上書き合戦が頻発します。
BEMが役立つ具体的なシーン
こうした大規模開発では「誰がどこで書いたCSSか分からない」ことがトラブルの原因になります。
BEMは次のような場面で効果を発揮します。
- 1.チーム開発でのクラス衝突回避
- 例:btnというクラスが複数人によって定義され、色やサイズが食い違う
BEMなら「header__btn / footer__btn」のように分けることで衝突を防げる - 2. コンポーネント単位での再利用
- BEMのBlockは「独立した部品」として設計するため、他ページに移植しても崩れにくい
特にECの「商品カード」や「レビュー一覧」などで効果的 - 3. 状態やバリエーションの明示化
- 例:カートに商品が入っているときだけ色を変える場合、「cart–active」のように状態が分かりやすい
チーム全体で「どういうときに使うクラスか」が即理解できる
実際の業界での採用例
- 大規模ECサイト:商品カードやランキング表示など共通UIが多いため、コンポーネント管理の恩恵が大きい
- ニュースメディアやポータルサイト:大量のコンテンツをテンプレート化するため、BEMでの明示的な管理が適している
- 受託制作の現場:複数の制作会社・外部パートナーが関わる場合、命名規則の統一で「誰でも理解できるCSS」を目指せる
注意点 ─ すべての案件で必要とは限らない
ただし「BEMが業務で役立つ場面=すべての案件」とは限りません。
- 小規模コーポレートサイト
- LPやキャンペーンページ
こうした案件では、BEMよりも軽量な命名ルールやTailwind CSSのようなユーティリティファーストの方が効率的です。
BEMの有効性の裏にある課題へ
BEMは確かに大規模開発では役立ちます。
しかし同時に、クラスが長くなる・HTMLが読みにくくなるといったデメリットも存在します。
次回は「BEMのデメリットと現場での評価」について、より掘り下げて解説していきます。
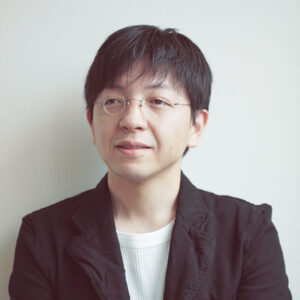
- 執筆者:西部俊宏
- 株式会社Webの間代表取締役。上場企業でのSEOやWebサイト構築実績多数。ECサイトのカスタマイズ経験も多数あり。
- 会社概要はこちら
「ECサイトをより便利にしたい」「もっと集客したい」ECカスタマイズはお任せください